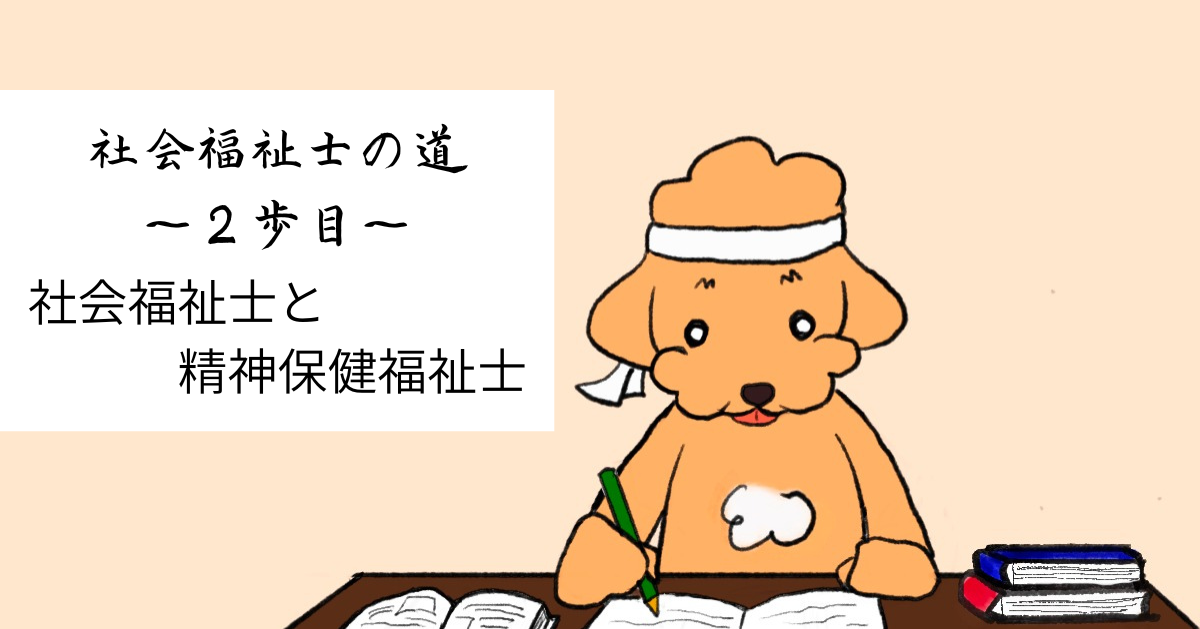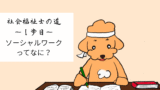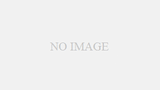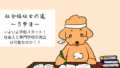こんにちは、mocoです。
今回は、社会福祉士を目指すうえで欠かせない基礎知識である「社会福祉士」と「精神保健福祉士」について、わかりやすく解説していきます。
これらの違いや役割をしっかりと理解していないと、学習のスタートラインにも立てません。この記事を通して、両資格への理解を深め、今後の学習に役立てていきましょう!
社会福祉士と精神保健福祉士ってなに?
”法的理解”と”ソーシャルワークとして”の2つの視点からみた社会福祉士と精神保健福祉士をまとめていきたいと思います。
法的の社会福祉士と精神保健福祉士
社会福祉士
1987年に制定された『社会福祉士及び介護福祉士法』に定められた国家資格で同法第2条(社会福祉士の定義)ではこのように記載されています。
社会福祉士登録簿に登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者。
少し堅い表現ですが、要するにこういうことです↓
福祉士登録簿に登録され、「社会福祉士」の名称を用いて、日常生活に支障のある方(身体・精神の障害や環境的な理由による)に対して、専門知識と技術をもって相談・助言・指導・福祉サービスを提供し、医師などの他の専門職と連携して支援(=相談援助)を行う専門職です。
精神保健福祉士
1997年に制定された『精神保健福祉法』に定められた国家資格で同法第2条(精神保健福祉士の定義)ではこのように記載されています。
精神保健福祉士登録簿に登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。
こちらも難しい表現が多いですが、簡単にまとめると以下のようになります↓
精神保健福祉士登録簿に登録され、「精神保健福祉士」の名称を用いて、精神障害を抱える方の相談・助言・指導・訓練などの支援(=相談援助)を行う専門職です。医療機関や社会復帰施設、地域での生活支援などを通じて、精神的な課題を抱える方の生活をサポートします。
ソーシャルワークとしての社会福祉士と精神保健福祉士
社会福祉士と精神保健福祉士は、ソーシャルワークの専門職です。
そのため、単に資格を持つだけでなく、ソーシャルワークの専門性――すなわち、専門的な知識、実践的な技術、支援に対する価値観、そして高い倫理観を備えることが求められます。
ソーシャルワークとは、困難を抱える人々が自分らしく生活できるよう支援し、社会的なつながりを回復・強化する実践です。社会福祉士や精神保健福祉士は、その理念を体現する実務家として、クライエント(支援を必要とする人)の立場に立ち、他職種と連携しながら支援を行います。
こうした役割を果たすために、常に自己研鑽を重ね、専門職としての責任と倫理に基づいた実践が求められます。
ソーシャルワークについてはぜひこちらも参照してください!
ソーシャルワークの専門職とは
社会福祉士や精神保健福祉士は、ソーシャルワークの専門職にあたります。では、そもそも「ソーシャルワークの専門職」とはどのようなものでしょうか。
まず、ソーシャルワークのグローバル定義をご紹介します。
ソーシャルワークは社会変革と社会開発、社会的結束および人々のエンパワメントと開放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。
社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。
ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基礎として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。この定義は、各国及び世界の各地域で展開してもよい。
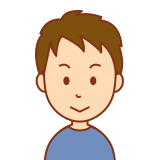
エンパワメントと開放を促進とかウェルビーイングって何だろう?
エンパワメントの開放を促進と何?
個人の問題だけでなく、社会構造的な障壁の解消にも取り組むことで、
人々が自らの力を取り戻し、抑圧から自由になっていけるよう支援することを意味します。

福祉の現場では、対象となる人々が自分自身の可能性を発揮し、
自立した生活を送ることができるようサポートするという考え方だよ。
ウェルビーイングって何?
ウェルビーイングとは、
自分にとっての「いい感じの状態」や「満たされた気持ちでいられること」を意味します。
ウェルビーイングには、次のような特徴があります:
- 自分で「満たされている」と感じられること(主観的)
- その状態がずっと続いていること(持続的)
- いくつかの要素が関係し合っていること(多様性)

たとえば、身体の健康だけでなく、心の落ち着き、人との関係、住んでいる環境など、いろんなことが影響しあって、「その人なりの幸せ」や「心地よい暮らし」がつくられていくんだよ。
まとめ
ここまで、「社会福祉士」と「精神保健福祉士」とは何か、そしてそれぞれに求められる資質や役割についてご紹介してきました。
社会福祉士は、社会福祉士登録簿に登録され、「社会福祉士」の名称を用いて、さまざまな生活上の困難を抱える人々に対して支援を行う国家資格です。同様に、精神保健福祉士も精神障害を持つ方々に特化した支援を行う国家資格であり、医療や地域社会と連携して、社会復帰や生活支援を行う専門職です。
どちらもソーシャルワークの専門職として、以下のような力が求められます:
- 専門的な知識
- 実践的な技術
- 支援に対する価値観
- 高い倫理観
これらを基に、人々の「福祉の向上」を目指して支援を行います。
最後に、「社会福祉士」や「精神保健福祉士」の仕事の根幹にある福祉の考え方についてまとめておきます。
福祉とは、単に「困っている人を助ける」だけではなく、すべての人がその人らしく、安心して生活できる社会を築くことです。以下のような側面をバランスよく満たすことが福祉の基本です。
- 健康:身体的・精神的に健やかであること
- 経済的安定:生活に必要な収入や資源が確保されていること
- 社会とのつながり:家族・地域・社会との良好な関係を持っていること
- 教育:必要な知識やスキルを得る機会が保障されていること
- 安全:暴力や差別、災害などから守られていること
社会福祉士や精神保健福祉士は、これらの福祉の要素を支え、調整し、人々が自己決定と尊厳を持って生きられる社会の実現を目指して活動しています。
これらの要素がバランスよく満たされてることで、個人や社会全体が幸福で充実した生活を送ることができる状態であると捉えられます。

福祉とは「困っている人を助けること」だけではなく、
すべての人が安心して自分らしく生きていける社会をつくる仕組みなんです。