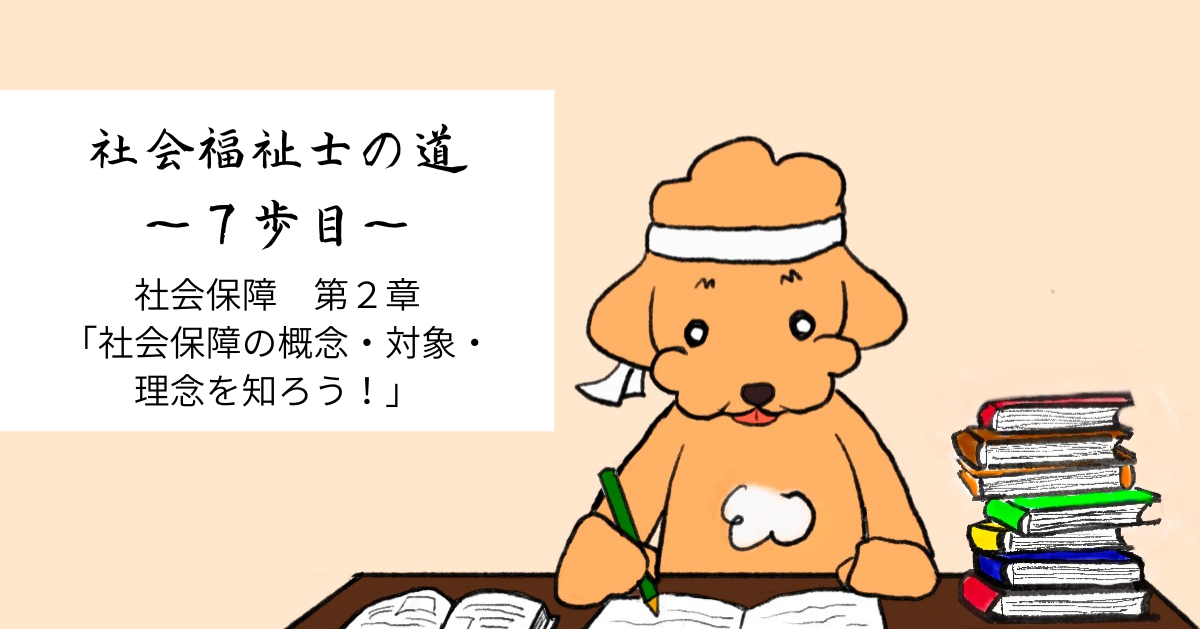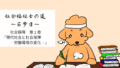みなさん、こんにちはmocoです!
日本の社会保障制度は、私たちの「安心して暮らす権利」を守るために欠かせない仕組みです。
病気、失業、高齢、障害、子育てなど、人生のさまざまなリスクに直面したとき、公的な制度がどのように生活を支えてくれるのか――それを理解することは、社会福祉を学ぶ上での第一歩です。
この記事では、1950年の社会保障制度審議会による勧告を出発点に、社会保障の「概念」と「範囲」について整理します。
国や時代によって異なる社会保障の定義を確認しながら、日本における制度の位置づけを明確にしていきましょう!
第1節 社会保障の概念と範囲
① 社会保障制度審議会による社会保障概念と定義の多様性
現在の日本における社会保障の概念の出発点となったのは、1950年の「社会保障制度審議会」による『社会保障制度に関する勧告』(いわゆる1950年勧告)です。
――――――――――――――――――
いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険の方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低限度を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。
――――――――――――――――――
この1950年勧告は、日本における社会保障の定義として広く用いられてきました。しかし、社会保障制度全体を包括的に定める統一的な法律が存在しないため、これが公式な唯一の定義として確立しているわけではありません。
また、国内外の社会保障の教科書を見ても、国・時代・学者によって社会保障の定義は異なり、多様性があることがしばしば明記されています。
② 社会保障の範囲
社会保障の基本的な考え方や本質的な要素については共通の理解があるものの、その範囲や内容には国や地域によって違いがあります。
- イギリス:所得補償に関わる諸制度を主に指す。
- アメリカ:社会保障制度、特に年金保険制度を指すことが多い。
※1930年代に世界で初めて「社会保障」という名称を含む法律(社会保障法)が制定されました。 - ILO(国際労働機関):年金保険、労災保険、医療保険、失業保険、家族手当(児童手当)などを社会保障として取り上げています。
③ 社会保障の概念の定義
近年、社会保障に期待される役割はますます多様化しています。日本の現状を踏まえると、さまざまな立場と両立しうる柔軟な定義が適していると考えられます。
したがって、本稿では学習教材で提示された以下の定義を採用します。
「広く国民を対象として、個人の責任や自助努力では対応しがたい社会的リスクに対し、公的仕組みを通じて給付を行うことにより、穏やかで安心できる生活を保障すること。」
4.社会保障制度の体系と種類
社会保障制度は、「保障の方法」と「制度の目的」という2つの観点から分類できます。以下に、日本の現行制度をもとにした代表的な分類を示します。
① 保障の方法に着目した分類
| 制度の種類 | 主な制度 |
|---|---|
| 社会保険 | 医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険 |
| 公的扶助 | 生活保護、生活困窮者自立支援制度 |
| 社会手当 | 児童手当、児童扶養手当、特別障害手当、特別児童扶養手当 |
| 社会福祉 | 障害福祉、児童家庭福祉、高齢者福祉に関する諸制度 |
各制度の特徴
- 社会保険:保険料を財源とし、加入者に対して給付を行う仕組み。
- 公的扶助:保険料ではなく公費によって生活困窮者を支援する制度。
- 社会手当:子育てや障害、ひとり親世帯など、特定の条件に該当する人々に対して現金給付を行う制度。
- 社会福祉:上記の制度では十分に対応できない個別的な生活支援のニーズに応じ、主に現物給付を通じて支援を行う制度。
| 制度区分 | 財源 | ミーンズテスト(資力調査) |
|---|---|---|
| 社会保険 | 保険料+公費 | 無 |
| 公的扶助 | 公費 | 有 |
| 社会手当 | 主に公費 | 無、または緩やかな基準あり |
※ミーンズテストとは、資産や所得の状況に基づき給付の可否を判断する仕組みを指します。
② 制度の目的に着目した分類
| 分類 | 主な制度 | 内容 |
|---|---|---|
| 所得保障 | 年金保険、労災保険(休業補償給付など)、雇用保険、社会手当、生活保護 | 失業・疾病・障害・高齢などによる所得喪失を補う。 |
| 医療保障(健康保障) | 医療保険、労災保険(療養補償給付など) | 疾病や傷害の治療、健康の維持・回復を支える。 |
| 介護保障 | 介護保険 | 要介護状態の人々に対し、介護サービスを提供。 |
| 社会福祉(福祉サービス保障) | 障害福祉、児童家庭福祉、高齢者福祉、生活困窮者自立支援制度 | 個々のニーズに応じた福祉サービスを公平に提供。 |
社会保障は、国民の生活を支える大切な仕組みであり、時代や社会状況の変化に応じてその内容も進化しています。
私たち一人ひとりがその意味と範囲を理解することが、安心して暮らせる社会づくりへの第一歩となります。
まとめ
- 社会保障の概念は、1950年の社会保障制度審議会勧告を出発点として形成された。
この勧告では、国民が「文化的社会の成員としての生活」を営めるよう、公的責任による経済的保障を行うことが明示された。 - 日本には社会保障制度を包括的に定めた統一的な法律が存在しないため、社会保障の定義には多様性がある。
国や時代、研究者によって社会保障の範囲や重点が異なるのが特徴である。 - 社会保障の範囲は国によって異なる。
- イギリス:主に所得補償制度を指す
- アメリカ:年金制度中心の狭義の社会保障
- ILO:年金・医療・労災・失業・家族手当など幅広く定義
- 日本の社会保障制度は、
「保障の方法」(どう支えるか)と 「制度の目的」(何を支えるか)という二つの視点から整理できる。- 保障の方法:
- 社会保険(保険料+公費)
- 公的扶助(公費+ミーンズテストあり)
- 社会手当(特定条件の現金給付)
- 社会福祉(個別ニーズへの現物給付)
- 制度の目的:
- 所得保障(生活費の補償)
- 医療保障(健康の維持・回復)
- 介護保障(介護支援)
- 社会福祉(個別的な福祉サービス)
- 保障の方法:
- 現代の社会保障の定義は、
「個人の責任や自助努力では対応しにくい社会的リスクに対して、公的な仕組みで給付を行い、安心して生活できるようにすること」
と整理される。
社会保障は、私たち一人ひとりが安心して暮らせる社会の基盤です。
その概念や仕組みを理解することは、福祉の専門家だけでなく、すべての市民にとって重要な学びとなります!