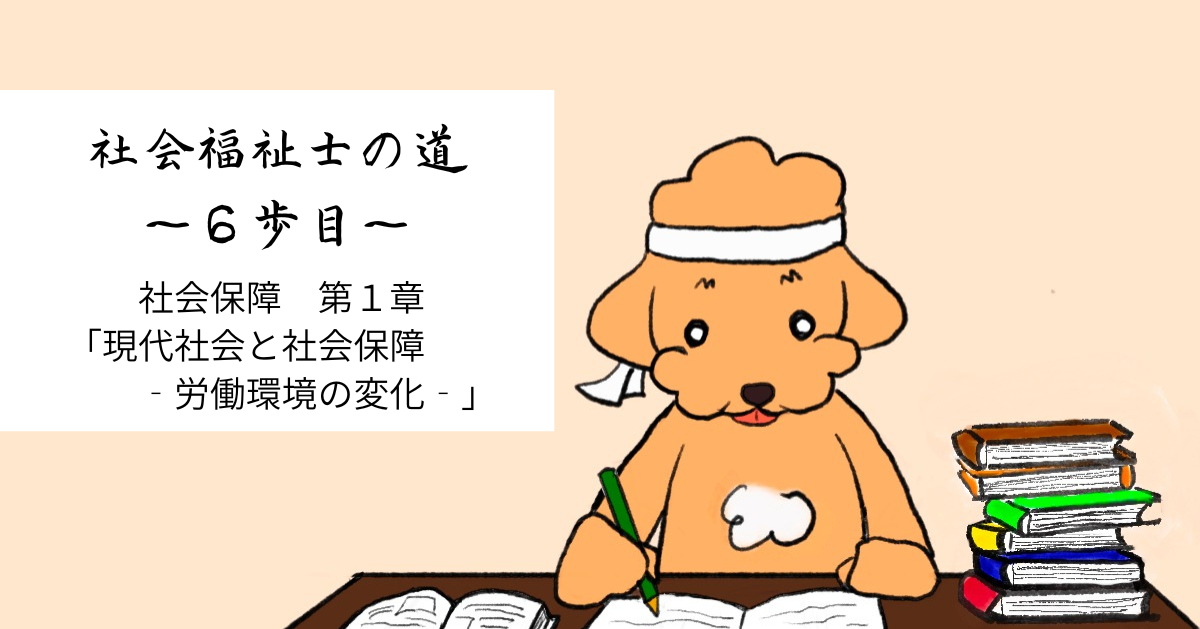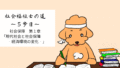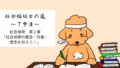こんにちは!mocoです。
今回は労働環境の変化についてです。
学習のポイントはこちらです↓
- 労働力と失業、非正規雇用の状況等の労働環境の変化について理解する
- 雇用・労働の変化がもたらす影響について学ぶ
- 雇用・労働政策と社会保障の課題について考える
これらのポイントを軸にまとめていきたいと思います。
第1節 雇用・労働の動向
近年、日本の労働市場は大きく変化しています。働き方の多様化や高齢化社会の進展、そして女性の社会進出など、労働を取り巻く環境は確実に動いています。ここでは、最新のデータをもとに日本の「労働力」「失業」「雇用形態」の変化を整理します!
1 労働力の状況
2023年時点で、日本の労働力人口は6,925万人。そのうち就業者は6,747万人で、3年連続の増加となりました。
就業者に占める被用者(会社員など)の割合は90.1%と高く、就業率も61.2%と上昇傾向にあります。特に15〜64歳の労働力人口比率は81.1%と高い水準です。
男女別に見ると、依然として女性の就業率は男性より低いものの、晩婚化や育児休業制度の充実によって、結婚・出産後も働き続ける女性が増えています。その一方で、女性の非正規雇用率が高いという課題も残ります。
また、65歳以上の就業率は25.2%と過去最高水準。年金支給開始年齢の引き上げや定年延長などが影響し、「働く高齢者」が当たり前の時代になりつつあります。
2 失業
2023年の**完全失業率は2.6%**と、過去20年で大幅に改善しています。2002年の5.4%、2010年の5.1%と比べると、雇用の安定が進んでいることがわかります。
若年層(15~34歳)の失業率も改善しており、全体としては「働く場」が広がってきています。
しかし、若年無業者は59万人、35~44歳の無業者も37万人と、就業意欲を失った層が一定数存在しています。単なる失業率の改善だけでは見えない、「働く機会の質」や「キャリア形成支援」の重要性が浮き彫りになっています。
3 正規・非正規雇用の現実
2023年のデータでは、
- 正規雇用者数:3,615万人(9年連続増加)
- 非正規雇用者数:2,124万人(2年連続増加)
- 非正規雇用率:37.0%
と、非正規雇用が依然として高い割合を占めています。特に55〜64歳で44.1%、65歳以上で76.8%が非正規雇用というデータからも、高齢者が年金だけでは生活できず、就労を続けている現状が伺えます。
4 雇用・労働の動向のまとめ
- 労働参加の多様化
女性や高齢者を中心に、働き方の幅が広がり「生涯就労社会」へと進化しています。 - 非正規雇用の固定化
女性や高齢層に偏る非正規雇用が、所得格差の一因となっています。 - 若年層の無業問題
数字上の失業率は改善しても、社会とのつながりを失う若者が依然として存在。支援が必要です。 - 高齢者雇用の質の確保
働く意欲があっても、健康・待遇・再雇用の条件が課題として残っています。
第2節 雇用・労働の変化がもたらす影響
かつて日本では「終身雇用」や「年功序列」といった、安定を前提とした雇用慣行が社会の基盤でした。
しかし近年、グローバル化や経済構造の変化を背景に、雇用のあり方は大きく変化しています。ここでは、サービス業の拡大や雇用の流動化、そしてワーキングプアの増加が日本社会に与える影響を整理していきます!
1 サービス業の拡大と雇用の流動化
日本経済において、製造業中心からサービス業中心の産業構造へと転換が進む中、従来の「日本的雇用システム」は見直されつつあります。
これまでのように、長期雇用を前提とした終身雇用・年功賃金制度に代わって、
- 短期間・短時間の有期契約労働
- 派遣労働や請負契約(業務委託)
といった柔軟な雇用形態が増加しています。
その一方で、企業が契約を自由に解除できるようになった結果、
「派遣切り」や「雇止め」などの問題が深刻化しています。
また、形式上は請負契約でありながら、実際には発注元から直接指揮命令を受ける「偽装請負」も社会問題となりました。
福祉・介護現場にも広がる請負・ギグワーク
請負労働は製造業だけでなく、ホームヘルプサービスやデイサービスの送迎など、介護・福祉分野にも広がっています。
最近では、単発の仕事をアプリなどで請け負う「ギグワーク(単発労働)」も増加中です。
しかしこうした働き方は、雇用契約を前提とする従来の社会保障制度(雇用保険・厚生年金など)の枠組みから外れてしまうことが多く、保障の空白が生まれているのが現状です。
2 ワーキングプアの増加と社会への影響
一方で、失業率の改善が進む一方で、働いていても生活が苦しい人(ワーキングプア)が増加しています。
その背景には、
- 非正規雇用や請負労働の拡大
- 労働基準法・労働契約法などの規制緩和による労働保護の後退
が挙げられます。
つまり、雇用の安定を犠牲にして「柔軟性」を重視した結果、政策的にワーキングプアが生まれたとも言えるのです。
経済への影響:消費の低迷とデフレの長期化
ワーキングプア層の増加は、単なる個人の問題ではありません。
低所得・不安定就労によって将来設計が難しくなり、
- 結婚や出産をためらう
- 消費活動が抑制される
といった影響を通じて、デフレ経済の長期化や税収の減少につながります。
社会保障への影響:無保険・無年金リスクの拡大
日本の社会保障制度は、かつて正社員(特に男性)を中心に設計されていました。
そのため、非正規労働者の社会保険加入が徐々に拡大しているとはいえ、
勤務時間や雇用形態の条件から外れる人も多く、無保険・無年金状態に陥るリスクが残っています。
今後、こうした人々が高齢化することで、社会保障の持続性にも大きな影響を与えることが懸念されています。
3 雇用・労働の変化がもたらす影響のまとめ
日本の雇用構造は、今まさに「安定から柔軟へ」と転換の時期を迎えています。
しかしその裏で、
- 雇用の不安定化
- 所得格差の拡大
- 社会保障制度の空洞化
といった問題が進行しています。
「多様な働き方」を支える制度やセーフティネットの整備が、これからの日本社会の大きな課題となるでしょう。
第3節 日本の雇用・労働と社会保障の課題
バブル崩壊以降、日本の雇用環境は大きく変わってきました。
かつての「終身雇用・年功序列」に支えられた安定した労働社会は姿を変え、非正規雇用や短期契約といった柔軟な働き方が広がっています。
日本の雇用・労働政策の変遷と、それに伴う社会保障の課題について整理していきます!
1 ワークフェア政策の展開
1990年代以降、日本では「完全雇用」や「男性稼ぎ手モデル」に基づく旧来の雇用システムから転換が進み、「ワークフェア(Workfare)」と呼ばれる就労促進型の政策が展開されてきました。
政府は失業者の増加に対応するため、企業がより柔軟に人材を採用できる仕組みを整備しました。主な法整備は以下の通りです。
就職促進の流れ
- 1985年 労働者派遣法:派遣労働のルールを定める。
- 1993年 パートタイム労働法:短時間労働者の待遇改善を目的。
- 2007年 労働契約法:多様な働き方を法的に位置づけ。
これらの制度改正によって、非正規雇用や請負労働が拡大し、企業にとっては「雇いやすい」環境が整った一方、労働者の安定性は低下していきました。
再就職支援と「積極的労働市場政策」
失業者への再就職支援としては、
- ハローワークでの職業相談・職業訓練
- 雇用保険の教育訓練給付制度
などが行われ、「積極的労働市場政策」と呼ばれています。
就職氷河期の影響と長期的課題
長期不況が続いた平成時代には「就職氷河期」が到来。新卒者が職を得にくくなり、多くのフリーターやニートが生まれました。
その世代が今では40代に差し掛かり、
- 非正規雇用として働き続けている
- 社会保険に未加入のまま生活している
という状況が多く見られます。
結果的に、ワーキングプア(働いても生活が苦しい層)として社会保障の枠外に取り残されるケースも少なくありません。
2 障がい者・女性に対する雇用政策の拡充
日本では、労働市場から排除されがちだった人々(障がい者、女性)の就労支援も進められてきました。
障がい者雇用政策
1960年 障害者雇用促進法が制定され、企業に対し障がい者雇用率を義務化。
障がいを理由とする差別の禁止、合理的配慮の提供なども明文化されました。
女性の雇用政策
1972年 男女雇用機会均等法により、募集・昇進・解雇などでの性差別を禁止。
→ 改正により、妊娠・出産・育休を理由とした不利益扱いやセクハラ防止も義務化。
1991年 育児・介護休業法では、結婚・出産・介護による離職を防ぐ仕組みが整備されました。
しかし、障がい者や女性の多くは依然として非正規雇用に偏り、十分な所得や保障を得にくい現実があります。
これにより、社会保険制度の網から漏れ、公的扶助を受けにくいという問題も生じています。
3 ワークライフバランスと働き方改革
長時間労働や過労死、少子化の深刻化を受け、「ワークライフバランス(仕事と生活の調和)」という考え方が注目されました。
政策の流れ
- 2007年:「仕事と生活の調和憲章」制定
- 2010年:「行動指針」策定
- 2018年:「働き方改革関連法」施行
この法律では、
- 長時間労働の是正
- 柔軟な働き方の推進(テレワークなど)
- 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
が掲げられています。
課題と現実
働き方改革は、表面的には「柔軟な働き方」を支える取り組みですが、
実際には、非正規雇用や短時間勤務の拡大によって、低賃金・不安定雇用が広がる側面もあります。
また、勤務時間の短縮が収入減につながり、逆に生活が苦しくなる労働者も出ています。
このような「多様な働き方」をどう社会保障で支えるかが、今後の最大の課題といえるでしょう。
4 ワークライフバランスと働き方改革のまとめ
ワークフェア政策は失業者の就労促進を目指す一方で、非正規雇用の拡大を招いた。
就職氷河期世代では非正規・低所得層が固定化し、社会保障の「空白地帯」が生まれている。
障がい者・女性雇用政策は制度的には進展したが、所得や保障面での格差が依然として残る。
働き方改革はワークライフバランスを推進する一方で、所得減や不安定労働の問題を伴う。
今後は、多様な働き方を支える社会保障の再設計が求められている。
まとめ
日本の雇用・労働環境は、終身雇用から非正規・多様な働き方へと大きく変化しました。
この柔軟化は雇用の幅を広げる一方で、所得格差や社会保障の不安定化を招いています。
就職氷河期世代や女性、障がい者などが不安定な立場に置かれる現状を踏まえ、
今後はすべての人が安心して働けるよう、雇用形態にかかわらず支援と保障を再構築することが求められます。