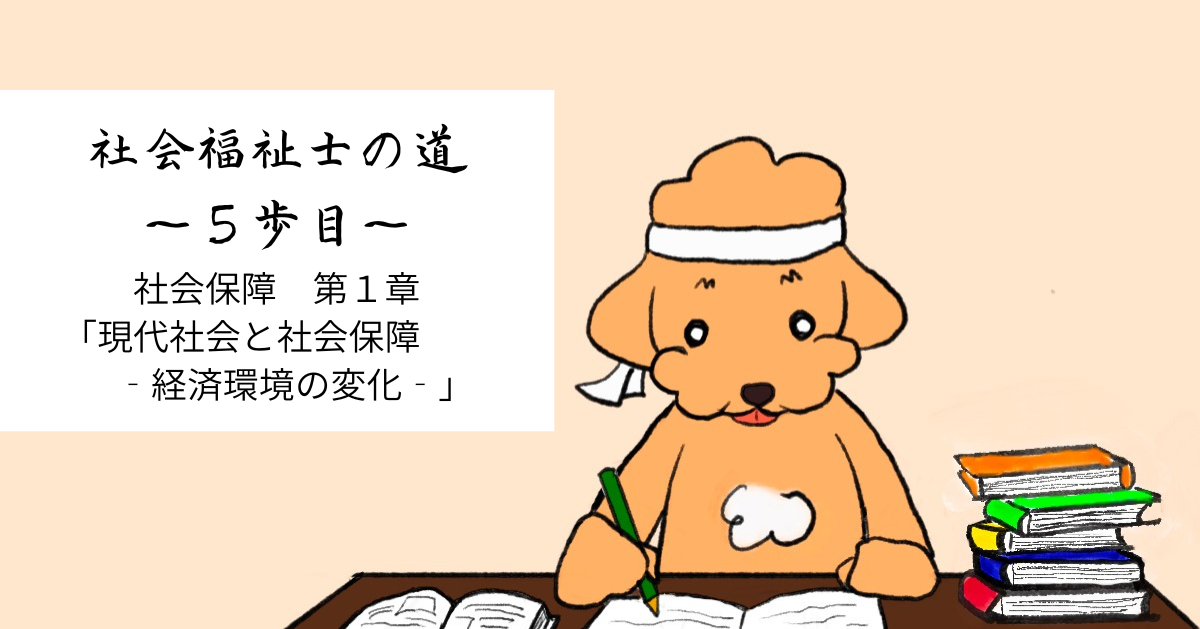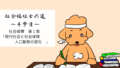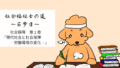こんにちは!mocoです。
今回は社会保障にとって経済環境の変化がもたらす影響と課題についてまとめたいと思います!
経済の動きは社会保障に大きな影響を与えます。
経済が良好であれば雇用や所得が増え、税収が増加し福祉が充実します。反対に、景気が悪化すれば失業や貧困が増え、社会保障がより強く求められるようになります。
そのため、社会保障制度を理解するには、経済成長や国民所得、財政政策などの経済環境の変化を知ることが欠かせません!
第1節 経済環境の変化
「経済環境の変化」を勉強するうえで3つのポイントに注目します。
- 経済成長、国民所得を中心とする経済環境の変化について理解する。
- 低成長経済化における国民の所得、貯蓄、負債の状況について学ぶ。
- 経済・財政政策の課題について学ぶ。
1 経済成長と国民所得
経済成長を示す「GDP」
経済の動きを測る代表的な指標が国内総生産(GDP)です。GDPは、1年間に国内で生み出されたすべての財やサービスの付加価値の合計であり、その伸び率が経済成長率を示します。
内閣府によると、2023(令和5)年の日本の名目GDPは591兆4,820億円で、名目成長率5.0%、実質成長率1.0%でした。
日本のGDPはアメリカ、中国、ドイツに次いで世界第4位ですが、1人あたりのGDPは約448万円(世界第34位)と、生産効率の面では高くありません。
分配の視点から見る「国民所得」
GDPが生産面に焦点を当てた指標であるのに対し、国民所得は国民にどれだけ分配されたかを示します。
2022年度の国民所得は409兆円(前年度比3.3%増)となっています。
経済指標の限界と新たな価値観
GDPや国民所得は「儲けの総額」を示すものであり、市民によるボランティア活動やシェアエコノミーが活発になっても数値には反映されません。
そのため、ブータンの「国民幸福度(GNH)」のように、幸福や持続可能性、文化の多様性、社会関係資本といった経済以外の豊かさを重視する考え方が広がっています。
2 低成長経済下の国民生活
所得の減少と格差の拡大
厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、2023年の全世帯の平均所得は524.2万円、高齢者世帯では304.9万円でした。
1994(平成6)年の664.2万円から100万円以上減少しており、長期的に所得は下がっています。
また、全世帯の平均所得を下回る世帯は多く、
100〜200万円未満:14.6%
200〜300万円未満:14.5%
300〜400万円未満:12.9%
と、中低所得層の割合が高い状況です。
年齢別では「50〜59歳」が最も高く309.4万円、「70歳以上」は193.5万円と、年齢による格差も見られます。
貯蓄と負債の現状
総務省「家計調査報告」によると、2023年の2人以上世帯の平均貯蓄残高は1,904万円。しかし、平均を下回る世帯が全体の約3分の2を占めています。
さらに、貯蓄が100万円未満の世帯が多く、金融資産を保有していない「貯蓄ゼロ世帯」は単身で36.0%、2人以上世帯で24.7%にのぼります。
一方、負債を抱える世帯は全体の約4割(39.3%)。そのうち91.8%が住宅・土地関連の借入です。
高齢者世帯の純貯蓄額は2,425万円と高い水準ですが、世代間格差が広がっているのが現状です。
3 経済政策と社会保障の課題
グローバル化と持続可能性
現代の経済はグローバル化が進み、ヒト・モノ・カネが国境を越えて移動しています。
この動きの中で、金融経済が実体経済から乖離し、一部の企業や投資家に富が集中するようになりました。
また、AIやビッグデータ、IoT(モノのインターネット化)といった技術革新が進み、「第4次産業革命」とも呼ばれる変化を生んでいます。
一方で、地域経済の中心となるサービス業は、雇用や消費生活を支え、地域住民の安心や信頼を生み出しています。
グローバル経済と地域経済のバランスを取り、環境保護や人権、持続可能性に配慮した経済政策が求められています。
社会保障・税一体改革と今後の課題
日本では、経済成長と財政再建を両立するために「社会保障・税一体改革」が進められました。
2011(平成23)年に成案が決定し、2012(平成24)年には「社会保障制度改革推進法」が成立。
年金・医療・介護・少子化対策を重点分野とし、消費税を安定財源とする仕組みが整えられました。
この改革は「持続可能な社会保障」と「財政健全化」の両立を目指しましたが、グローバル経済で広がった所得格差の是正という点では課題を残しています。
今後は、税や社会保障を通じて所得再分配の機能を強化することが求められています。
4 まとめ
社会保障の仕組みを考えるうえで、経済の動きを理解することは欠かせません。
経済が人々の生活を支え、社会保障がその生活の安心を守る。
この2つは、まさに車の両輪のような関係にあります。
私たちがより豊かで安心して暮らせる社会をつくるためには、
経済の成長だけでなく分配の公平さを保つこと、
格差の拡大を防ぎ、支え合える社会を目指すこと、
地域や地球全体の持続可能性を意識すること、
が大切です。
経済と社会保障の関係を知ることは、「福祉とは何か」をもう一度考える第一歩になるのではないでしょうか。