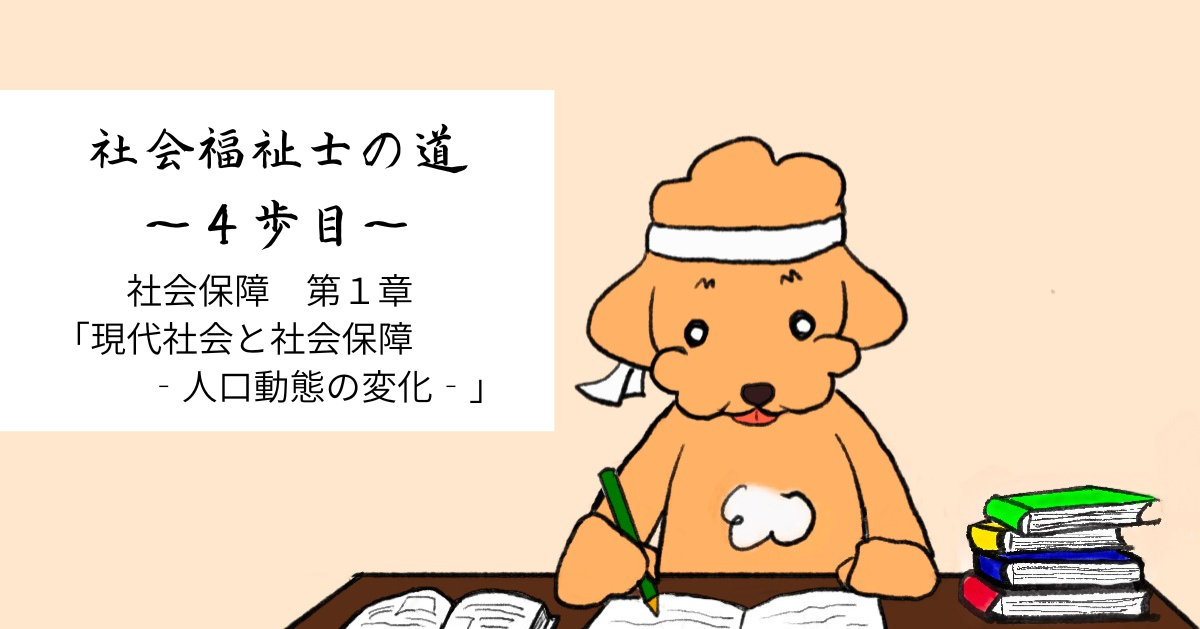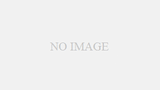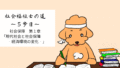こんにちは、mocoです。
9、10月は「社会保障」について一緒に学んでいきたいと思います。
第1章のテーマは 「現代社会と社会保障」 です。
社会保障は、私たちの暮らしを支える重要な仕組みですが、そのあり方は常に社会の変化とともに姿を変えてきました。
この章では、社会保障の政策課題や解決の方向性を考えるために、現代社会の動きを整理していきます。
特に、社会保障を支える基盤として大きく影響を与える次の3つの観点に注目します。
- 人口動態の変化
- 経済環境の変化
- 労働環境の変化
これらを手がかりに、現代社会における社会保障の課題を一緒に考えていきましょう!
第1節 人口動態の変化
「人口動態の変化」を勉強するうえで3つのポイントに注目します。
- 人口減少と少子高齢化を中心とする人口動態の変化について理解する。
- 人口減少と少子高齢化が社会及び社会保障に与える影響を考える。
- 少子化対策と社会保障の課題について理解を深める。
1 人口減少と少子高齢化
① 日本の総人口の変化
日本の総人口は2023(令和5)年10月1日時点で1億2435万人となっており、総人口は2008(平成20)年に1億2808万人でピークを迎え、2011年(平成23年)から減少し続けています。
日本の総人口は明治初頭の1870年代から1990年代にかけて急激な増加を経験してきました。2000(平成12)年前後には安定化して、2008年(平成20)年にピークを迎えました。
そして政府の推計によれば今後も総人口は減少し続け、2070年に8700万人になるとみられています。
こうした日本の状況は「人口減少社会」と表現されています。日本にとって長期的な人口減少は初めての経験であり、社会の様々な部分でダウンサイジング(縮小や見直し)が求められることを意味しています。
② 少子高齢化
人口の変化は人数の問題だけでなく、年齢構成の変化においても特徴があります。それは人口の高齢化です。
高齢化が進む主な要因は、平均自明が伸びることと出征数が減ることにあります。出生数が減ることを少子化と呼び、高齢化が進むことと少子化をまとめて「少子高齢化」と表現します。
一人の女性が一生の間に産む子どもの数の平均を合計特殊出生率という数字であらわします。
日本のこれまでの推移は以下の通りです。
| 年表 | 合計特殊出生率 | 備考 |
|---|---|---|
| 1930-1940代前半 | 3から4前後で推移 | 1914(昭和16)年に閣議決定された「人口政策確率要綱」では「産めよ、殖やせよ」というスローガンが掲げられ、出産が推奨されていた。 |
| 1950年代初頭 | 3を下回る | |
| 1975(昭和50)年 | 2を下回る | ※1971(昭和46)年~1974(昭和49)年には第2次ベビーブーム(団塊ジュニア世代)があったが、 それは人数の多い第1次ベビーブーム世代の多くが出産したことによるもの。 |
| 2005(平成17)年 | 1.26 | |
| 2023(令和5)年 | 1.20 | 過去最低 |
一方で、日本の高齢化率は29.1%、75歳以上の人口が16.1%となっており、その割合の高さは世界第一位です。75歳以上の人口が65歳以上人口の半数を超えていることも特徴です。なお、15歳未満人口は11.4%、15~64歳(生産年齢人口)は59.5%となっています。
日本の平均寿命は、男性が81.09歳、女性が87.14歳であり、いずれも国際的に見て極めて高いです。
2 人口減少と少子高齢化が社会に与える影響
人口減少し、少子高齢化が進む社会では生産年齢人口が減ることで様々影響が現れます。
その影響について学んでいきたいと思います。
① 経済への影響
人口減少により人手不足になると、消費者人口も減少することを意味しています。買い手が減ってモノが売れなくなるので経済成長が滞ると論じられています。
さらに人手不足を補おうとして生産性を上げ、同時に消費が縮小していくと、生産が過剰になって物価が下がり、デフレがもたらされることになります。
消費者人口減少による買い手不足やデフレなどは経済背長にとって大きなダメージとなると考えられています。
しかし、生産性の高い産業を拡大させ、利益を分配できれば、人口減少はむしろ一人当たりの所得を増やすメリットをもたらす可能性もあります。
② 地域社会への影響
人口減少は、地域社会にも大きな変化をもたらします。
まず、住民が減れば税収も減るため公共サービスの削減につながり、水道、交通、消防、清掃、図書館、学校といった印蔵を維持することが困難になります。また、商店街や自治会・町内会の衰退、田老行事や伝統文化の継承問題など、暮らしに直接かかわる地域の社会資源や文化が失われることもあり、地域・コミュニティの衰退に伴って住民のこりつかや分断が進行していきます。
日本創生会議が2014(平成26)年に問題提起した「消滅可能都市」という議論で、「消滅可能性」がある市町村は896に上り、全自治体のほぼ半数が当てはまるとされています。
また、民間の有識者会議である人口戦略会議は、2024(令和6)年4月に「地方自治体『持続可能性』分析レポート」を公表し、2020(令和2)年から2050(令和32)年の30年間に若年所税(20歳から39歳)人口が50%以上減少する自治体を「消滅可能性自治体」と定義し、該当する自治体が744に上ると分析しています。
地域社会が崩壊し、コミュニティの衰退と孤立化が深刻化すると、子育てがますます困難になり、心理的にも子育てをリスクと捉える悪循環に陥ってしまいます。地域社会の崩壊は、選択的に子供を産む人を一層減らし、子供がいることが不利な社会をつくってしまうのです。
③ 社会保障への影響
少子高齢化によって社会保障の担い手が減ると税収や保険料収入が減少することで制度の維持ができなくなると懸念されています。
少子高齢化で影響を受けやすい税収としてはまず年金保険(国民年金)です。
世代間扶養の考え方(賦課方式)で財源を賄っている部分が大きいため影響を受けやすいとされています。また、医療保険や介護保険も支え手がいなくなることで影響を受けています。
また少子化で、単身世帯・こなし世帯が増加することで既存の社会保障制度の基盤を揺るがすことにもつながります。日本の社会保障制度は核家族(男性稼ぎ手モデル世帯)を前提とし、世帯を単位に保険に加入する仕組みを取ってきたため、今後世帯ではなく個人単位にすべきといった構造そのものを見直す必要があります。またこうした世帯単位の社会保障は、家事労働や介護を女性に追わせてきた側面があり、ジェンダー不平等を前提としてきた社会保障制度の在り方が問われるようになると予想されます。
3 少子化対策と社会保障の課題
政府は1990年代半ばあたりから、社会保障政策や労働政策を通して多彩な「少子化対策」を進めてきました。その対策と人口政策の課題を説明します。
① 少子化対策の進展
| 年表 | 政策 | 備考 |
| 1994(平成6)年 | エンゼルプラン | |
| 2001(平成13)年 | 待機児童ゼロ作戦 | 待機児童問題対策。 |
| 2002(平成14)年 | 少子化対策プラスワン | 子育てと仕事の両立支援だけでなく、「地域における子育て支援」を推進。 |
| 2003(平成15)年 | 次世代育成支援対策推進法 | 企業等の従業員に対する有給休暇や育児休業の取得強化、労働時間の短縮等に関する行動計画の策定等が義務付けられた。 |
| 2003(平成15)年 | 少子化社会対策基本法 | |
| 2004(平成16)年 | 少子化社会対策大綱 | 少子化社会対策基本法に基づいて策定され、総合的かつ長期的な少子化に対処するための政府の指針。 大綱の重点課題に沿って、「子ども・子育て応援プラン」となる具体的なせっさく会対策基本法に基づいて策定され、総合的かつ長期的な少子化に対処するための政府の指針。大綱の重点課題に沿って、「子ども・子育て応援プラン」となる具体的な施策と目標が提示される。 |
| 2008(平成20)年 | 新待機児童ゼロ作戦 | 待機児童問題対策。 |
| 2010(平成22)年 | 子ども・子育てビジョン | 少子化社会対策基本法に基づく新たな大綱として閣議決定される。 |
| 2013(平成25)年 | 待機児童解消加速化プラン | 待機児童問題対策。 待機児童は政治の重点課題と認識される。 |
| 2015(平成27)年 | 少子化社会対策大綱を継承したあらたな大綱の策定 | 「若い年齢での結婚・出産の希望の実現」「多子世帯への一層の配慮」「男女の働き方改革」と重点課題が示される。 |
| 2016(平成28)年 | ニッポン一億総活躍プラン | 待機児童の解消、保育士の処遇改善、放課後児童クラブの整備等の推進、さらに「希望出生率1.8」と「人口1億人の維持」に向けた取り組みを推進。 |
| 2017(平成29)年 | 人づくり革命 | 経済政策の柱として掲げられ、待機児童の解消だけでなく、幼児教育の無償化および高等教育の無償化(高等教育の就学支援新制度)などの改革が進められた。 家庭の教育費負担を軽減させる形での子育て支援 |
| 2018(平成30)~2020(令和2)年度 | 子育て安心プラン | 待機児童の解消や女性就業率の8割をめざす「子育てプラン」を取り組む。 |
| 2021(令和3)~2024(令和6)年度 | 新子育て安心プラン |
② 少子化対策という人口政策の課題
2016(平成28)年2月に解消されない待機児童問題がSNSをはじめニュースや国会で注目されたり、前後して「保活」という造語も作られるなど、子どもを保育所に預けられたに「働く女性」現状が社会問題となりました。
同時にこれは子育てが女性に依存している現状が浮き彫りにした形になります。
少子化対策は就労する女性をターゲットにした支援策として考えられる傾向があり、就労する男性が子育てすることを含めた子育て家族を支える社会を構築する課題には十分に応えられていないのが現状です。
このように少子化対策は総人口を維持するための人口政策としての性質が強く、家族支援策およびケアの社会化を図る政策としては課題が残されています。
また人口の自然増(出産による人口増)を導くことが困難であるなかで、人口の社会増(流入による人口増)として外国人労働者の受け入れを拡大による「人材確保」が模索されています。
2008(平成20)年には日本とインドネシア、フィリピン、ベトナムとの間で締結された経済連携協定(EPA)により、外国人看護師・介護福祉士候補者の受け入れが開始されました。
その後も出国管理及び難民認定法の改正によって、新たな在留資格を加えることで「外国人労働者」の受け入れを実質的に拡大していく政策がすすめられています。
| 例 |
|---|
| 外国人技能実習制度に介護の枠を追加 |
| 在留資格「特定技能」「特定活動」 ※農業・建設・ビルクリーニング等の様々な業種で就労しながら日本に在留できるようになる。 |
| 外国人技能実習制度は「育成就労制度」へと改正され、外国人労働者の権利の保護とキャリア形成を支援する方向性が示される。 |
これまでの外国人労働者の受け入れ拡大を狙った残留資格制度は、長期間家族を形成して日本で暮らすことを想定しておらず、移民を受け入れないまま「労働力」だけを受け入れる性格が強かった。
これからは外国にルーツを持つ人々が日本で家族を築き、子どもを産み育てる選択肢を持てる社会にしていく視点で社会制度及び社旗保障制度の見直していくことが求められています。