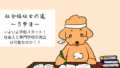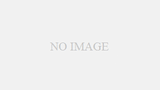あなたは失敗を全部「自分のせい」にしていませんか?
仕事がうまくいかないとき、あなたは原因をどこに求めますか?
「自分のせい」でしょうか、それとも「仕事や上司、同僚のせい」でしょうか。
心理学では、原因を自分に求めることを自責思考、他人や環境に求めることを他責思考と呼びます。
自責思考
成長のきっかけをつかみやすい一方、やりすぎると自己肯定感が下がり、精神的負担が増える。
他責思考
自分を守る手段になる一方、成長機会を逃すことや人間関係を悪化させるリスクがある。
どちらも一方に偏るのは危険です。大事なのは「使い分け」。でも、渦中にいるときほどそのバランスを見失ってしまうものです。
私が陥った「自責一色」の働き方
私は今、仕事をしながら社会福祉士の勉強をしています。当初は勉強の内容をブログで定期的に発信する予定でした。しかし、学校が始まった直後に職場で大きな変化が起きました。メンバーが突然退職し、その業務を私が丸ごと引き継ぐことに。業務量は単純に2倍、残業は月80時間、翌月も70時間。さらに他のメンバーは休みがちになり、上司からは「マネジメント不足」と責められる毎日。人員補充を求めても、人件費を理由に必要最低限しか増員されず、障がい者雇用で働けないメンバーも1人分としてカウントされるため、結局誰かがその穴を埋め、限界を超えた人から辞めていく…そんな悪循環が続きました。気づけば終電まで働く日々。それでも私は「できないのは全部、自分の能力不足のせい」と信じ、必死に食らいついていました。しかし3ヶ月近く経った今、心が限界に近づいていました。
「逃げるのは嫌い」だった私が気づいたこと
私は昔から、環境や誰かのせいにするのは嫌いでした。でも、心が壊れかけたとき、ようやく気づいたんです。
他責思考は“逃げ”ではなく、“心を守るための手段”だということ。
誰かや環境のせいにすることは、自己正当化ではなく、自分の心の健康を守るための選択肢でもある。そう思えるようになってから、少し呼吸が楽になりました。
転職活動と社会福祉士への道
今は転職活動を進めています。勉強と現職の両立に加えての活動は正直つらいですが、「このまま壊れるよりマシ」と思っています。
そして、社会福祉士を取得した暁には、今回の経験を障害者雇用の改善に役立てたい。苦しい経験も未来の糧にできると信じています。
忙しいときこそ、自分を回復させる時間を持つ
これまでは休日、疲れ果てて寝るだけの日も多かったですが、今後は積極的に外に出て、明るい話題をブログで発信していきたいと思っています。外出して感じたことや楽しかった出来事は、自分のメンタルケアにもなるからです。
最後に──頑張るか、離れるかを決めるために
自責も他責も、どちらか一方に偏りすぎると心は疲弊します。自分では判断が難しいときは、利害関係のない第三者に相談し、「まだ頑張る」か「いったん離れる」かを客観的に選択してください。
あなたの心を守ることは、甘えではありません。それは、これからも前に進むための大切な準備なのです。